|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 『サメ革』の価値 『サメ革』の価値 |
|
|
|
| 刀剣と武士とサメ革の絆 |
|
|
|
|
サメ革の用途の第一は刀剣の装飾であった。
これらが用いられたのは、ずいぶんと古いことと思うが古墳から出土した刀剣にはまだ見つかっておらず、現存する最古のものは、正倉院の「金銀鈿荘唐刀(きんぎんでんそうからたち)」である。
この唐大刀は、サメ革を巻いた刀の現存する最古かつ、最良の物であり、サメ革の粒の形はごく自然に絶妙に揃っていて、中央に見事な親粒を配置し、色は白くもなく黄色っぽくもない優美な象牙色で、良く研ぎ澄ました白米を見るような奥深い光をとどめ、匂うばかりの艶というにいわれぬ品位がある。
サメ革がいつ頃から刀剣に使用されたかを知る資料はなく、古墳から出土する上代の環頭大刀や、頭槌大刀などにまだサメ革は見られず、中国においても「呉物志」や「後漢志」「本草音義」などの文献上では見られるのであるが、まだ実物資料は不明である。
この所中国や韓国では考古学調査の発展がめざましい事から、やがてサメ皮を用いた刀剣資料が発見されると思われるが、おそらく中国で唐風の新様式かそれとも唐以前に用いられていたのが奈良時代にわが国に伝わり日本で発達したものと考えられる。
それでは、なぜ刀剣にサメ革を巻いたのだろうか、常識的に考えると、サメ革には粒々があるので手が滑らず握りを固定させる効果があったからだと考えられている。
刀の柄に必要な条件は、手になじみやすく血糊や水に濡れても滑らない事、堅固で長持ちする事、美しく、しかも加工しやすい事である。
この条件をすべて満足させるような材料は、そうざらにないはずだ。
又サメ革ならどんなサメ革でもというわけにいかず、ほとんどが輸入品を用いていた為、実用と装飾のみの理由ではなく稀少価値もその一つである。
しかし、その他にどうしてもサメを使用しなければならぬ理由があった。
それはサメは威力あるものの象徴とされていたのと同様に刀剣も霊力の象徴であったからだ。
柄鮫として用いたサメ皮は国産の物は用いず全て舶来品に頼っていた。
室町時代は勘合貿易で明や南蛮から、また呂宋助左衛門や角倉了以、伊勢の角屋七郎次郎などの朱印船で運ばれ、鎖国の時代も長崎と唯一の門所としてオランダ船で輸入されていた。
柄鮫の名称はサメの産地名でよばれ、最上級品をチャンペという。
占城(チャンペ)とは現在のベトナム中部から南部にかけインドネシア系のチャム族が建国した国で、二世紀末から十七世紀の終わり頃まであり、ここで取れたサメを最上等品とした。
上質なサメ革が、ほとんど純金の目方と同じ価値にあったといわれているほど入手困難で貴重だった。
柄巻師辻京二郎氏が、かつて入手された見事なサメ革には、安政年号で「代金十五両七分」と書付があった。
当時の刀匠荘司直胤の新作刀は十両であった事から見ても、その貴重さがうかがえる。
サメ革の良否の目利は鮫問屋にそれぞれ専門家がいて、自然のなせる粒の配置とバランスで値をつけていた。
こうした中から目利が厳選した最高級品は、「千両鮫」と称され錦や金襴で飾り「餝(かざ)り鮫」とか「献上鮫」といって水引で美しく飾った箱に入れ、豪商などから諸侯や殿様への高級贈答品とされた。
武士は、実用的には何の効果もないサメ革の模様になぜ不思議なほどに凝っていたのであろうか?
稀少価値を重んじる趣味の世界の評価はとても当事者でなければ理解できない物だが、日本の武器は西洋のそれと異なり、常に平和への願いをこめた武器であり、相手を殺す為のものが眺めていると戦う心が浄化され、鋭利さだけを求めずに美しいものに憧れをこめて無駄な虚栄を飾ることにより殺す為の武具が生かす為の武具へと昇華すると考えられていたのかもしれない。
サンドペーパーがなかった時代サメヤスリといって、サメ革が研磨用に広く用いられていた。
これに適する種類はコロザメ・カスザメ・ヨロイザメ・アイザメ・ネコザメなどで一尾の体の部分により粒の荒さが異なり色々な番手のヤスリが作られる為、便利とされていた。
昔は刀の飾りに用いていた残片をヤスリとして使用し、乾燥させた革をそのまま適当なサイズに切って使用したり、用途により板片や竹などに貼り付けて大正時代まで市販されていた。 |
|
|
| ▲TOP OF PAGE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
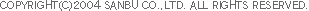 |
|

